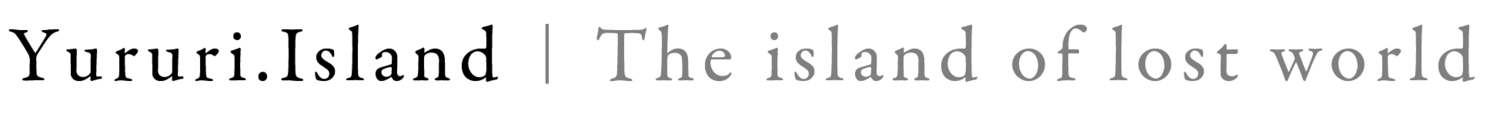Photographs
by Okada Atsushi
Since 2011, Okada has been filming wild horses inhabiting Yururi Island off the Nemuro Peninsula in Hokkaido, Japan.
|
深い霧の中に、霞みゆく馬の群れ。滑らかな陶器のように白く輝く雪原の上を駆ける馬……。写真家の岡田敦は10年以上にわたり、ユルリ島の情景を作品で紡いできました。立ち入りが厳しく制限され、広く知られる機会もなかった北辺の海に浮かぶ幻の島。その情景は、岡田の作品を介して人の心の中に宿り、馬は幻影となって、いまその島の上を走り出す……。
幻の島
Yururi Island | The island of lost world
撮影:岡田敦
制作年:2019-2020(撮影)
撮影地:ユルリ島
幻の島
写真家 岡田敦
2011年の夏、初めて根室半島の沖合に浮かぶユルリ島を訪れたとき、そこで眼にしたものは、失われゆく根室の自然を色濃く残した風景と、かつて昆布漁や馬産地として栄えたこの土地の歴史や風土が刻んだ痕跡であった。それらは、深い霧の中に埋もれ、忘れ去られ、ひっそりと沈んでゆく夕陽のように淡く僕を照らした。その残火のような光を写真の中に留めたことが、“消えゆくものたち”と交わした最初の対話だった。島の馬はいなくなる。そして、島の存在も忘れ去られるだろう……。あの夏、僕はいままさに終わりを告げようとする残照の中、一人、草原に立っていた。
“消えゆくものたち”との対話は静かに続いた。季節は淡々と島の上を通り過ぎ、僕はそのいくばくかの時間を馬とともに過ごした。島を覆う海霧が草原の中へと消えゆくと、野花は葉を落とし、馬は冬毛をまとい冬支度を始める。やがて島の空に雪が舞い、色あせた草原が白く塗り替えられると、星空が雪原を照らしはじめ、馬はその光の下で寄り添いあい、その日、最後に歩みを止めた雪の上で、ただ静かに眠りに就く。そして、島の断崖を覆う巨大な氷柱が徐々に解け、海鳥がそこでさえずりはじめると、島にはまた海霧の季節がやってくる。季節は淡々と島の上を通り過ぎる。そして、霧の中から現れる馬の群れは、年を追うごとにその頭数を減らし、やがてそれは“群れ”ではなくなった。
誰に頼まれるわけでもなく、拠点としている東京から島に通い、10年以上の時が過ぎ去った。“消えゆくものたち”と向き合う時間は胸に痛みを伴ったが、そこで眼にしてきたものを振り返ると、はかなくも、繊細で美しかった。それは、北の果ての海に図らずも生まれ、取り残され、残存していた、ある種の聖域のようにも感じられた。深い霧の中を一人さまよい、馬を探した夏の日に眼にした光景を、明星を頼りに雪原を歩き、馬とともに夜明けを迎えた冬の日の出来事を、僕は生涯忘れることはないだろう。地図上に描かれた架空の島のように、島は記憶の中に存在し、馬は写真の中で生き続ける。全てはたどり着くことのできない幻影となって……。しかし、辺境の海に浮かぶ“ユルリ”という名をもつその島は、深い霧の中でまだかすかな明かりをともしている。
岡田敦 / 写真家
1979年北海道生まれ。2003年大阪芸術大学芸術学部写真学科卒業、2008年東京工芸大学大学院芸術学研究科博士後期課程にて博士号(芸術学)を取得。同年“写真界の芥川賞”とも称される木村伊兵衛写真賞を受賞。その他、北海道文化奨励賞、東川賞特別作家賞、富士フォトサロン新人賞などを受賞。主な写真集に『I am』(赤々舎/2007年)、『ataraxia』(青幻舎/2010年)、『世界』(赤々舎/2012年)、『MOTHER』(柏艪舎/2014年)、『安田章大写真集 LIFE IS』(マガジンハウス/2020年)などがある。作品は北海道立近代美術館、川崎市市民ミュージアム、東川町文化ギャラリー、東京工芸大学写大ギャラリーなどに収蔵されている。
北海道根室半島沖に浮かぶユルリ島には2009年頃から関心を持つが、学術調査以外での上陸が認められておらず、2年近くにわたる交渉を経て、2011年に初めて渡島し撮影を行う。島には当時12頭の雌馬がいたが、雄馬はおらず、時代の変化とともに役割を終え、絶えることが決まっていた。撮影をはじめてから6年後の2017年には、島の馬は3頭となる。岡田の撮影の目的は、時代から取り残され、社会から存在を忘れられていた島の馬の姿を自身の作品の中に留めることによって、その存在を作品の中で生かし続けることであった。2023年ユルリ島での10年余りにわたる活動の記録をまとめた書籍『エピタフ 幻の島、ユルリの光跡』(インプレス)を発表し、同作品にてJRA賞馬事文化賞を受賞する。
生と死のあわいに浮かぶ島で
「青い星通信社」代表
元「東京カレンダー」編集長
星野智之
冒頭から個人的な話で恐縮だが、写真家・岡田敦にユルリ島の存在を教えたのは、私である。正確には憶えていないが、確か2008年か09年のことだったと思う。岡田が08年に“写真界の芥川賞”とも呼ばれる木村伊兵衛写真賞を受賞し、才能あふれる写真家としてその存在を知られるようになってから、さして間を置かない時期だ。
特別に深い意図があったわけではない。稚内に生まれ、札幌で育った岡田に「北海道に馬だけが暮らしている無人島があるらしいんだけど、知ってる?」といったごく軽い調子で、いわば“世間話”としてユルリ島を話題に出したと記憶している。だから数年後に岡田の口から、「いまユルリ島の馬の写真を撮っているんです」という言葉を聴いたときには、正直驚いた。あの島は立ち入りが制限され、上陸禁止となっているのではなかったか、と。
聴けば岡田は私の何気ない世間話を耳にした直後から、活動の拠点としている東京から何度となく根室に通い、市役所と粘り強く交渉を続け、そうしてようやく市役所やユルリ島の地権者である落石漁協から島での撮影の了解を取り付けたのだという。
その熱意はどこから生まれたものだろう? 岡田敦は言葉によって自らの作品の意図や制作の過程を説明することの極端に少ない写真家で、ユルリ島に関してもそうした撮影に至るまでの経緯を語られたことはほとんどないのだが、ただ岡田のこれまでの作品を振り返ってみると、彼がユルリ島に惹かれた理由についてはおぼろげながらも視えてくるような気もする。それはひと言でいえば、“生と死”の探究への渇望だ。岡田は上陸が禁止された無人島で、つまり誰にも見守られ、看取られることがない場所で、生きて、そして死んでいく馬たちの姿を見詰めたかったのだろう。そしてその生と死にただ単身で向き合いたかったのではないか。
生と死。実はそれは、岡田敦の写真に通底するテーマでもある。岡田が木村伊兵衛写真賞を受賞した写真集『I am』(赤々舎/2007年)は、リストカットを繰り返す女性の、ガラス細工の壊れ物を思わせる肖像を中心に構成されていた。その後の『世界』(赤々舎/2012年)では地震や津波という災厄の爪痕も生々しい地が、紛れもなく私たちの日常の世界と地続きであることが示された。『MOTHER』(柏艪舎/2014年)では女性の分娩の現場にレンズを向けることで、一人の人間の生の最初の瞬間を写真に刻んだ(まさにその瞬間から人は死に向かって歩みはじめるのだが)。こうした姿勢は岡田が撮影した写真集としては最新刊となる『安田章大写真集 LIFE IS』(マガジンハウス/2020年)にも明確に引き継がれている。ここに掲載された、脳腫瘍を患い、そこから帰還した若き表現者を被写体に据えた一連の写真群は、単なるアイドル写真集などという枠に収まりきれるものでは到底なく、一人の鋭敏な若者がめぐらす生と死についての思索を鮮烈なイメージに転換させた、独特の世界を構成している。
岡田にとってはユルリ島の馬たちは、彼がこれまでに出会ってきたそうした被写体にも似て、そのカメラのレンズを生と死というテーマにフォーカスさせる存在だったのではないだろうか。種馬となる雄を運び出されて以降、ユルリ島の馬たちから“誕生”の可能性が消えた。馬たちは一頭、また一頭と老衰による死を迎えていく。岡田がここ10年にわたって撮影してきた写真の中にあって、こうしてただ消滅へ向かう道を静かに進んでいく群れの姿は、根室沖の美しくも過酷な自然を背景にして、余剰をそぎ落とされた生と死の実相を我々の前に浮かび上がらせてみせるのだから。『I am』にフィーチャーされた女性の腕に刻まれた深い自傷の傷跡は、その一本一本がまるで生と死の境界線のようにも見えた。彼女はその境界を行きつ戻りつしていた。そしてユルリ島もまた、そんな境界の上に位置している。馬たちは生と死のあわいに浮かぶこの島の上で、従容として運命の道を進みながら、日々を生きているのだ。
人が立ち入ることができないユルリ島の情景を、写真と映像によって伝えた岡田の取り組みは話題を呼び、多くのメディアで「ユルリ」の名が登場する機会が増えた。それは確かに岡田敦という写真家の、一つの功績だろう。しかし同時に、このウェブサイトで見ることができる作品の意味は、ただそれだけに留まるものではないだろうとも思う。岡田敦という写真家の創作の熱源、つまり根本的なテーマが表出しているからこそ、これらは単なる記録写真、記録映像であることを超えて、人の心を打つのだ。一人の写真家のユルリ島をめぐる冒険の真価は、そこにあるに違いない。